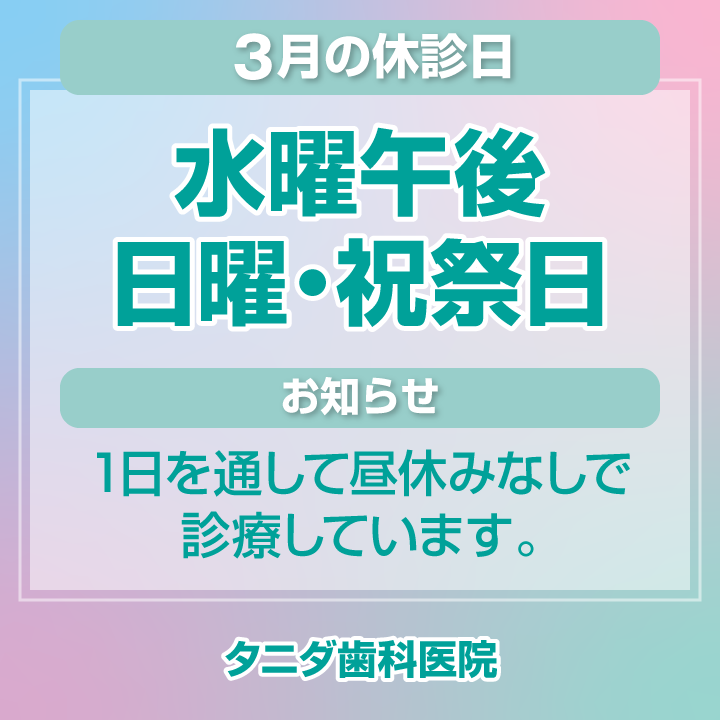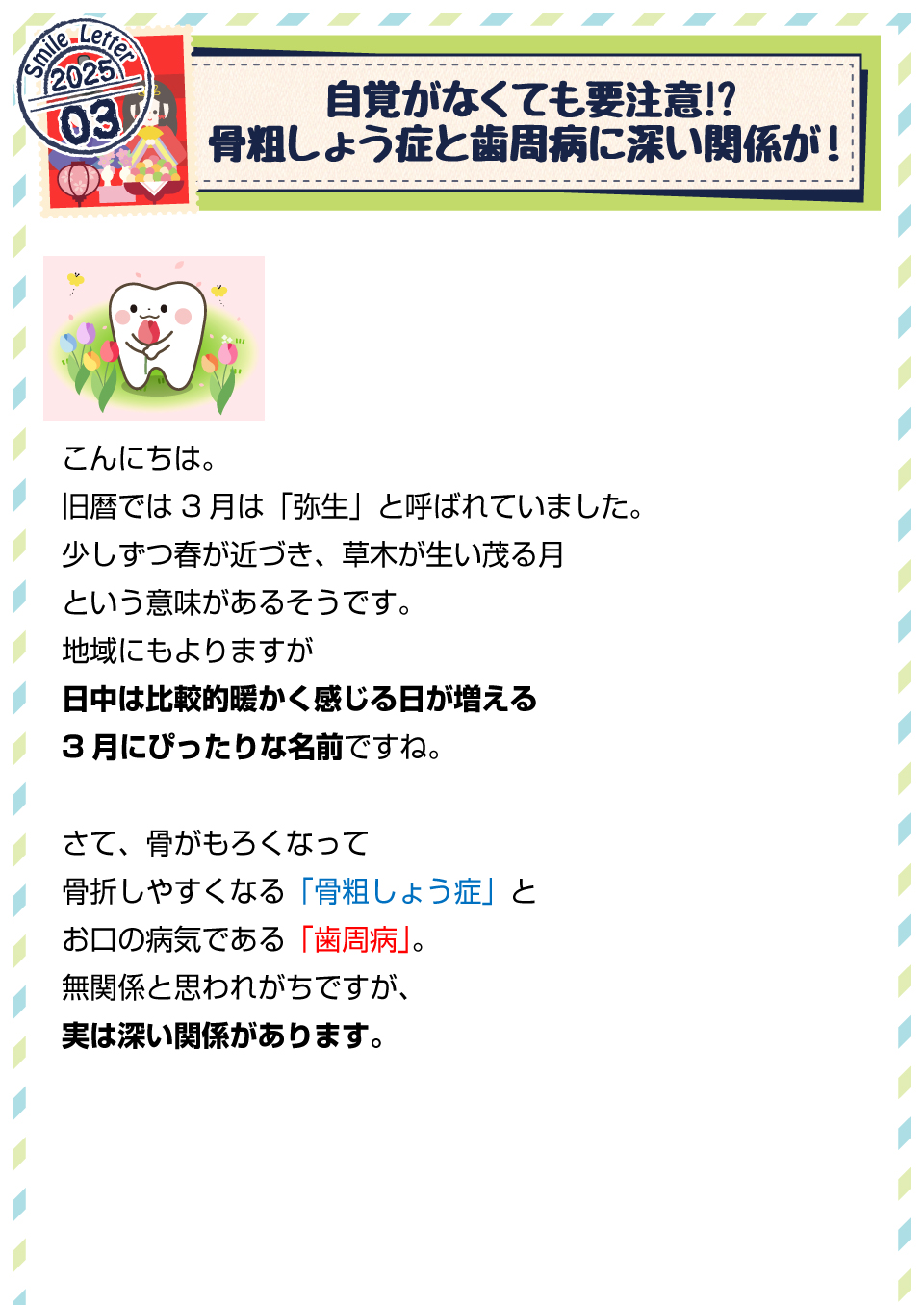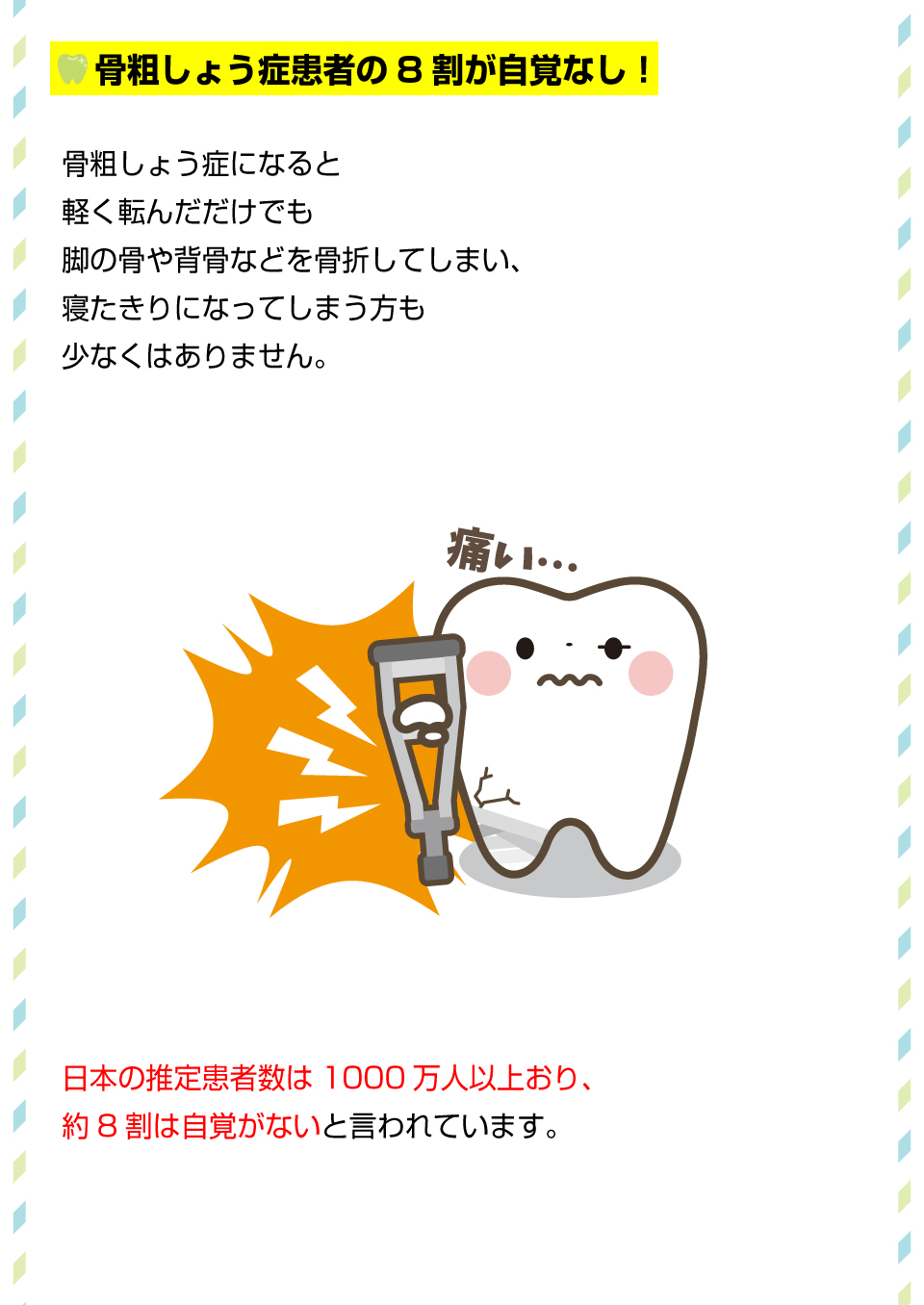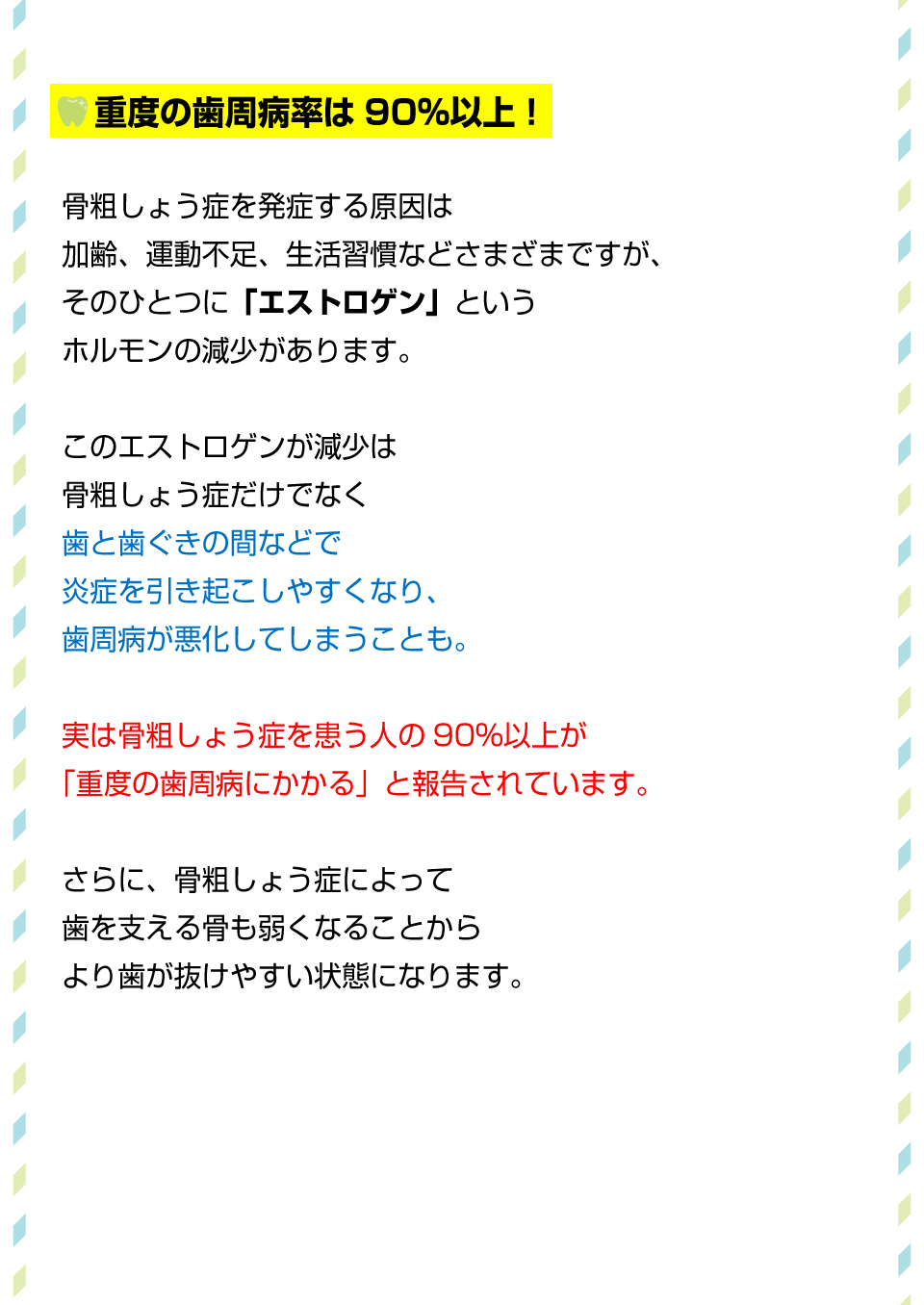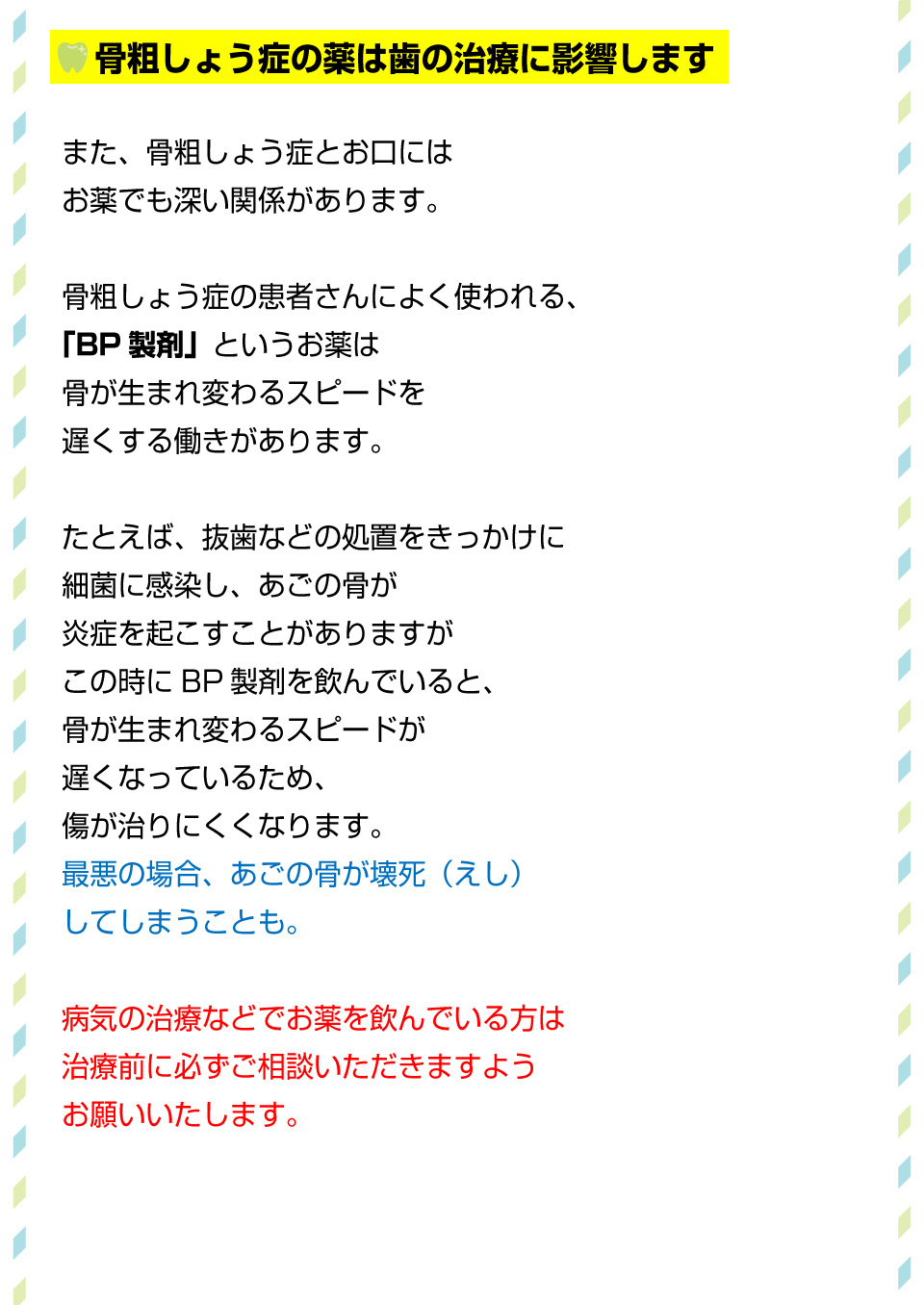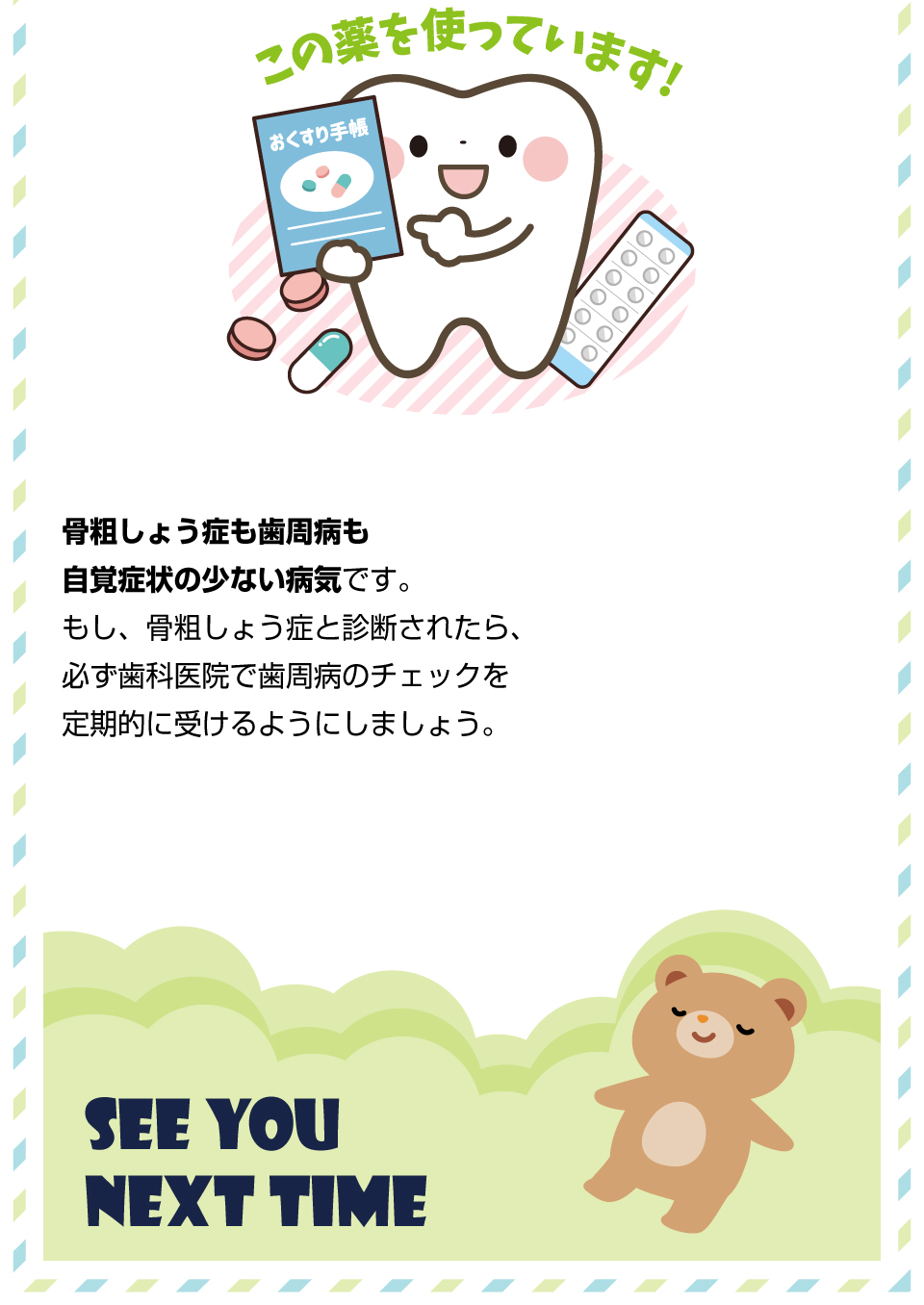高齢者の薬物療法-西宮市の歯科・歯医者ならタニダ歯科医院
西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。
高齢者の薬物療法
2025/03/06
こんにちは。訪問歯科医師の村山です。
前回まで、罹患患者数の多い高血圧症と糖尿病についてお伝えしました。今回は「薬(くすり)」についてです。
訪問診療を開始する方には必ずお薬手帳を提示して頂きその内容を確認します。小児では体重や年齢により薬物投与量を調整しますが高齢者ではその考えが低いためか多剤を多量に服薬しておられる方が多いです。老年者では加齢とともに薬物代謝・排泄の中心である肝・腎機能が低下するため薬物の血中濃度が上昇する傾向にあり、さらに高齢者では多くの疾患を有しているため多くの薬を同時に服薬することが多く、薬物間の相互作用で異常高値となる危険性が高くなります。肝機能や腎機能低下は通常自覚症状が全くないため、肝・腎機能の血液検査を行い確認するしか方法がありません。また高齢者では複雑な処方のため間違ってその内容を理解し、医師の処方意図と異なった服薬をすることが多くなるため、できるだけ簡単な処方(服薬回数を減らす、薬物を一包化する)を心がける必要があります。

老年者で起こりやすい臓器の変化から、特有の副作用が起こることもあります。脳梗塞の予防で汎用される抗凝固薬のワーファリンは、高齢者で出血の副作用が起きやすいため注意を要します。同じ血中濃度でも高齢者では臓器の感受性が亢進し、副作用が起こりやすい状態となることもあるのです。このように高齢者は薬物の副作用が起こりやすいが、その副作用が出現しても典型的な症状が起きにくいため、老年者に薬物を投与するときは積極的に副作用出現の有無に気を配る必要があります。老年者で多い高血圧、糖尿病では若年者と同程度の厳格なコントロールを行うと前述のような間違った服薬や臓器機能障害からくる血中濃度の過度の上昇から薬物が効き過ぎ、さらには過度の低血圧から失神や脳梗塞の発症、また低血糖から昏睡などの重篤な結果となりやすいので、血圧や血糖値を目標より多少高めにコントロールされている場合が多いのです。老年者では今後の罹病期間が若年者より短いので、生命予後に及ぼす影響が少ないといった点からもやや弱めの治療で十分かもしれません。
鎮痛薬は歯科でよく出される薬物の代表ですが、歯科以外でも老年者では腰痛、関節痛のため鎮痛薬を長期間服用していることが多いのです。特に長期間鎮痛薬を処方するときは胃・十二指腸潰瘍を起こしやすいので、他科で同じような鎮痛薬や副腎皮質ステロイドを処方されているかどうか、また消化性潰瘍を現在有しているか、既往があるかどうかなどを調べる必要があります。消化性潰瘍の既往のある者ではその発症率が特に高くなるのです。
「念のために痛み止めだけもらえれば…」
その考え方、危険な場合もあるのです。

歯の黄ばみ・くすみを解決!原因別の改善法
2025/03/04

こんにちは。院長の谷田です。
3月は桜をはじめとした花々が
全国的に咲き始めることから、
旧暦の別称で
「花見月(はなみづき)」や「花月(かげつ)」
とも呼ばれる月です。
きれいな桜の下での
お花見を楽しみにされている方も
多いのではないでしょうか。
季節ごとの花の色の移ろいは趣がありますが、
歯に関しては変わらない白さを保ちたいものです。
そこで今回は、歯が変色する原因と
対処法をご紹介します。
◆日ごろの食事も要注意!歯の表面の変色
鏡を見たときに気になる歯の黄ばみやくすみ。
これらの変色にはさまざまな原因があり、
それぞれ改善方法も異なります。
そのうち、歯の表面から変色する原因として、
以下のものが挙げられます。
・色素による着色
コーヒーやお茶、タバコに含まれる色素などが
歯の表面に付着することで、
黄ばんだりくすんで見えたりすることがあります。
・むし歯
初期の段階では白っぽくなりますが、
やがて進行すると歯に穴が開き、
黒っぽく見えるようになります。
・修復物(つめもの、かぶせもの)由来の変色
過去に歯の治療で使用した金属の修復物が
劣化することで金属部分が溶け出し、
黒っぽい色が着くことがあります。

◆歯みがきでは落とせない!?歯の内面の変色
歯の変色は先程のような
歯の表面への影響がイメージされがちですが、
実は、全く異なる原因で
歯の内面から変色することもあります。
下記にその例をご紹介します。
・神経をとった歯
過去の治療で神経をとった歯は、
時間が経つと黒く見えることがあります。
・加齢変化
加齢によって歯のエナメル質が薄くなる反面、
内側の象牙質は厚みを増します。
これにより、歯が黄ばんで見えるようになります。
・抗生物質による変色
歯が作られる時期に
テトラサイクリン系の抗生物質を服用すると、
象牙質の変色が起こり、黄色や褐色、
やがて暗紫色へ変色することがあります。

◆変色の原因に応じた改善法
歯の変色は見た目に影響を与えるだけでなく、
笑顔を見せるのをためらわせたり、
人と話すときに自信を失わせたりと、
心理面にも大きく影響します。
まずは、原因に合った改善方法を見つけていきましょう。
・表面の着色汚れにはクリーニングを徹底
飲食物由来の着色汚れは、
日常の歯みがきで
ある程度落とすことができます。
適正な分量の歯みがき剤を使用して
丁寧に磨きましょう。
また、歯にこびりついた頑固な着色は、
歯科医院で行う専門的なクリーニングで
きれいに落とすことができます。
・歯科治療で根本から解決
むし歯や神経のない歯、
薬剤が原因で生じた変色は、
歯のクリーニングなどでは改善できません。
これらのケースに対しては、
原因に応じた専門的な歯科治療が必要となるため、
歯科医院へ相談しましょう。
◆春の新生活、白く輝く歯で
自信ある笑顔を!
新しい出会いが増えるこの季節は、
清潔感のある白い歯が
周囲に与える印象をより魅力的にしてくれます。

歯の変色にお悩みの方は、
原因を明らかにして
適切な対処を行うためにも
お早めに歯科医院へご相談ください。
タニダ歯科医院
〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5
TEL:0797-61-2000
URL:https://www.tanidashika.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE
知覚過敏について
2025/02/27
こんにちは。歯科医師の井畑です。
寒波の襲来により寒い日が続いていますね。
冷たい空気によって歯がしみる時ががあります。
今回は知覚過敏についてお話ししたいと思います。
知覚過敏は、冷たい飲み物や酸味のある食べ物を
口にした時や冷たい風を感じると鋭い痛みとして、
多くの人が経験するお口のトラブルです。
その主な原因は以下の通りです。
・歯茎の退縮
加齢や歯周病が進行すると、歯茎が下がり、
象牙質が露出することで知覚過敏が発生します。
・酸性食品の摂取
柑橘類や炭酸飲料などの酸性食品を頻繁に摂取すると、
歯の表面が溶けやすくなり、エナメル質が薄くなります。
・歯の損傷
強いブラッシング、虫歯、亀裂、歯ぎしりによる
ダメージが歯を弱め、知覚過敏を引き起こすことがあります。

では、知覚過敏をそのまま放置するとどのようなリスクが
起こるのでしょうか。
それは以下のような問題が発生する可能性があります。
・症状の悪化
軽度の知覚過敏が放置されると、刺激に対する敏感さが増し、
食事や日常生活に支障をきたすようになります。
・虫歯や歯周病の進行
象牙質が露出している状態では、細菌が入り込みやすく、
虫歯や歯周病のリスクが高まります。
・歯の破損リスク
エナメル質がさらに失われると、歯が弱くなり、
欠けたり割れたりする可能性があります。
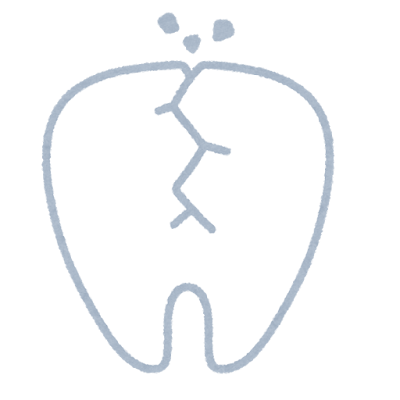
知覚過敏の症状を軽減するためには、
以下のようなセルフケアが効果的です。
・知覚過敏用歯磨き粉の使用
知覚過敏用の歯磨き粉は、刺激を遮断する成分(硝酸カリウムやフッ素)
を含んでおり、症状の軽減に役立ちます。
・柔らかめの歯ブラシの選択
硬い歯ブラシではなく、柔らかい毛の歯ブラシを選び、
優しく磨くことでエナメル質を保護できます。
・食生活の改善
酸性食品や砂糖を控え、バランスの取れた食事を
心がけることで、歯の健康を維持できます。
・力から歯を守る
睡眠中に無意識でやってしまう歯ぎしりの力から
歯を守る為にナイトガード(マウスピース)の使用を検討しましょう。

知覚過敏がセルフケアで改善しない場合は、
歯科医院での治療が必要です。以下は、一般的な治療法の一部です。
・コーティング材の適用
歯の表面に特殊なコーティング剤を塗布することで、刺激から歯を保護します。
・歯周病治療
歯周病が原因の場合は、歯茎の治療を行い、歯周ポケットの改善を図ります。
・神経治療
重度の場合、歯の神経を除去して症状を緩和する治療が選択されることがあります。
知覚過敏をそのままにしておくと、症状が悪化し、
歯の健康全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかし、適切なセルフケアや歯科医院での治療を行うことで、
症状を改善し、再発を防ぐことが可能です。早めの対応と予防策を実践し、
快適な日常生活を取り戻しましょう。